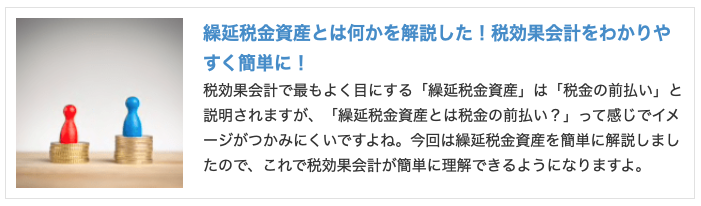繰延税金資産は、会計と法人税の処理タイミングのズレを調整する税効果会計で登場する資産です。この「ズレ」のことを「一時差異」といいますが、少し難しく聞こえるので、繰延税金資産と一時差異の関係をわかりやすく簡単に解説しました。
繰延税金資産と一時差異の関係
【税効果会計をわかりやすく簡単に72🤔】
✅繰延税金資産と一時差異の関係は?
繰延税金資産の根拠になるのが一時差異✅根拠?
一時差異は「会計と税法の損益処理のズレ」で「将来解消する」もの✅例えば?
賞与引当金
→賞与を実際に支給したら税法も費用処理を認める
→ズレ解消 pic.twitter.com/abeqahN4q8— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016_ac) 2019年6月16日
まず結論

それに税率をかけた金額が「繰延税金資産」
つまり前払いした法人税の金額です
会計と法人税では損益を認めるタイミングが違う
会計も法人税も「儲け」を計算しますが、考え方に差があります
それぞれが独立に「儲け」を計算するわけではなく、法人税は会計の儲け(=利益)に「考え方の差」を足したり引いたりして法人税の儲け(=所得)を計算します。
特に顕著に差があるのが、「費用」の取り扱いです。
特に費用は法人税の方が遅い
会計は「稼ぐ力」を決算書で明らかにしたいという発想に立っているので、「稼ぐ力」に少しでも陰りがみえたら、どんどん費用を会計帳簿へ記録していきます。
#減損会計とは #図解 #わかりやすく #ucd#減損会計とは #図解 #わかりやすく #ucd pic.twitter.com/UyMzjYVWvH
— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016) November 24, 2020
減損損失はその典型例で、特に売ったわけではなくても、稼ぐ力が落ちたら簿価を落とすという処理をしています。
一方で法人税は、「状況が同じなら誰が計算しても一緒の儲けになるように」という視点に立って儲けを計算します。
なので「発生が確実になった費用」だけを費用として認める傾向が顕著です。
そのため、会計と法人税では費用を認めるタイミングに差があるのです。

なぜなら、会計は既に過去に費用処理済みの費用を、法人税が後の年度で追加で費用(=損金)処理してくれるからです。
そのため税効果会計では、このズレのことを「将来減算一時差異」と呼んでいます。
ズレが解消するときに、利益・所得をマイナスする形で解消するからです。
そして、将来減算一時差異は、将来の法人税の儲けを減らしてくれるので、将来税金が「会計が計算した税金費用」よりも少なくなります。
これを税効果会計では、「税金の前払い」と呼んでます。
将来減算一時差異に税率をかけたものが繰延税金資産
繰延税金資産は、会計と法人税のズレが生じたときに発生します💡
例えば資産の評価損の否認🙅♂️とかで、会計は費用だけど法人税は一時的に損金じゃないとかです🔍 そうすると法人税が一時的に会計の想定よりも大きくなります🧐 これを税効果会計では「税金の前払い」と捉えて繰延税金資産と呼びます📝 pic.twitter.com/fuqUmgYKC5
— 内田正剛@会計をわかりやすく簡単に (@uchida016) January 25, 2021
実際に前払いになる金額は、将来減算一時差異の金額ではありません。
それに、税率をかけた金額が「実際に低くなる税金の金額」です。
なので繰延税金資産も、「将来減算一時差異」に税率(=法廷実効税率といいます)をかけた金額になります。