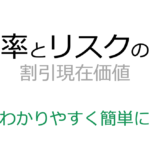
割引率とリスクの関係を図解で解説!割引現在価値をわかりやすく簡単に
割引現在価値計算で使う割引率は一定ではなく、会社や事業のリスクと関係があります。でも、本を見ると難しい用語が並んでいるので、サクッと理解したいですよね。そこで当ブログでは、割引率とリスクの関係を図解でわかりやすく簡単に解説します。
難しい会計を図解とやさしい文章でわかりやすく簡単に解説します。
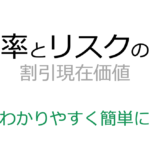
割引現在価値計算で使う割引率は一定ではなく、会社や事業のリスクと関係があります。でも、本を見ると難しい用語が並んでいるので、サクッと理解したいですよね。そこで当ブログでは、割引率とリスクの関係を図解でわかりやすく簡単に解説します。
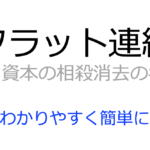
「フラット連結では投資と資本の相殺消去の仕訳はどうするの?」そんな疑問にお答えする記事です。理解のポイントは他の記事と同じで、あるべき姿との比較です。そこで今回は、フラット連結の投資と資本の相殺消去の考え方をわかりやすく簡単に解説します。
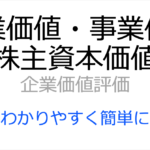
「企業価値・事業価値・株主資本価値って同じような意味に聞こえるけど違いは何?」 こんな感じで聞かれると、あれっなんだったっけと不安になる方がいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時は図解を使うと意外にサクッと理解できちゃいます。そこで今回は、企業価値・事業価値・株主資本価値の違いをわかりやすく簡単に解説します。
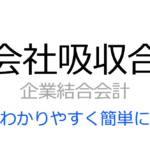
「子会社を吸収合併することになったけど、会計処理どうしたらいい?」 たしかに合併はたまにしかないイベントなので慣れにくい側面もありますが、「合併前後で何がどう変わるか?」を考えると意外とシンプルに見えてきます。そこで、企業結合会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、子会社の吸収合併の会計処理の考え方をお伝えします。
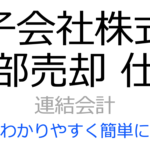
「子会社株式の一部売却の仕訳をサクッと理解したい」 たしかに連結会計のトピックの中でも何をしているのかイメージを掴みにくいトピックですよね。でもポイントはシンプルで、連結仕訳は何をしたいのか・全体像を押さえることです。そこで、1級商業簿記・会計学の解き方・考え方を解説するシリーズの今回は、子会社株式の一部売却の仕訳の考え方をわかりやすく解説します。
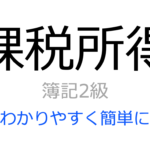
「課税所得って利益と何が違うの?」2級を勉強してると出てくる課税所得ですが、利益と違う感じに聞こえるので悩ましいですよね。そこで、2級商業簿記の解き方・考え方を解説するシリーズの今回は、課税所得を簡単にいうとどういうことなのかを、利益との違いとともにわかりやすく解説します。

EBITDAは企業価値評価などでよく見かける指標ですが、どういう意味なのか気になりますよね。DCF法とどういう関係にあるのかも知りたいところです。そこで今回は、EBITDAはどういう意味なのかを、企業価値評価やDCF法との関係とともにわかりやすく簡単に解説します。

「なんのために作るの?」「役割を知りたい!」はじめて法人税の申告書(別表1・次葉・別表4)を見られた方は、イメージしにくいと感じられたのではないでしょうか。ポイントは「法人税は儲けに課税」という部分です。そこで今回は、別表1と次葉と別表4はなんのために作る?役割をわかりやすく簡単に解説します。
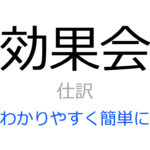
「税効果会計の仕組みはなんとなくわかったけど、仕訳が書けない」そんな悩みをお持ちではありませんか? 仕訳は問題文に書いてあるキーワードを拾うと、意外にサクッととけちゃいます。そこで、2級商業簿記の解き方・考え方を解説するシリーズの今回は、「税効果会計の仕訳の作り方の入門知識」をわかりやすく解説します。
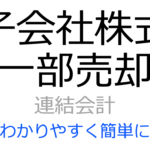
「子会社株式の一部売却の仕訳が解けなくて」たしかに連結会計の問題は何をしているかわからなくなる時がありますよね。とはいえ、難しい話はなく、持分計算表の作り方が押さえられれば意外にサクッと解けちゃいます。そこで、1級商業簿記・会計学の解き方・考え方を解説するシリーズの今回は、「子会社株式の一部売却の仕訳の解き方のヒント」をわかりやすく解説します。
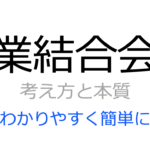
「企業結合会計ってボリュームが凄いんだけど、要するにどういうこと?」 はじめて会計ルールを見られた方は、ボリュームの凄さに驚かれたのではないでしょうか。たしかに、たくさんのルールが定められていますが、ポイントは「買った・持った・売った」で、普通の事業活動と同じです。そこで、連結・企業結合会計の本質を解説するシリーズの今回は、「企業結合会計の考え方」をお伝えします。
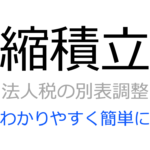
「圧縮積立金の会計処理が難しいし、税効果会計や別表の税務調整も考えるのはちょっと」そんな意識をお持ちの経理担当者の方がいらっしゃるのではないでしょうか。たしかに複雑なトピックですが、1つずつ紐解いていくと、意外にシンプルです。そこで今回は、圧縮積立金の別表調整(税効果会計あり)を数値例でわかりやすく簡単に解説します。
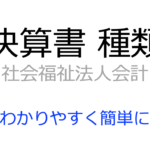
「社会福祉法人の決算書でどんな書類があって何がわかるの?」 はじめて目にされる方は、決算書からどんな情報が読み取れるのか気になりますよね。そこで、社会福祉法人会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、決算書の種類と内容をわかりやすく簡単に解説します。
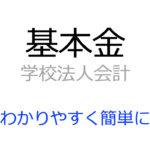
「基本金って株式会社の資本金と何が違うの?」そんな疑問をお持ちの経理担当者は少なくないのではないでしょうか。名前は似ていますが、かなり違うものです。そこで、学校法人会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、「基本金とは何か?」をお伝えします。
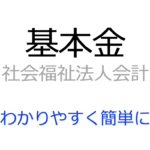
「基本金とは何だろう?」 たしかに株式会社の資本金と似ていますが、1文字違うので気になりますよね。実はかなり大きな違いがあります。そこで、社会福祉法人会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、基本金とは要するにどういう意味かをお伝えします。
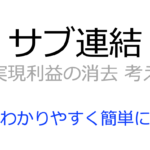
「サブ連結をする場合の連結財務諸表はどのように作るんだろう?」 連結担当を任されたものの、孫会社がいるグループだと簿記の教科書そのままとはいかず、悩ましいのではないでしょうか。サブ連結が網羅的に解説されている本もあまり見かけません。そこで今回は、サブ連結のパターンの連結財務諸表の作り方のうち「未実現利益の消去」にフォーカスしてわかりやすく簡単に図解で解説します。
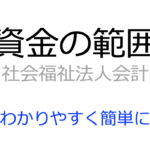
「資金って何だろう? なんとなくわかるんだけど」社会福祉法人の決算書では「資金収支計算書」をはじめ、(支払)資金という用語がよく出てきます。そこで今回は、社会福祉法人の会計で出てくる「資金」の範囲について、わかりやすく簡単に解説します。
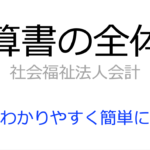
「決算書がいっぱいあってどれも似た名前だけど、作るのが漏れてないかな?」そんな疑問をお持ちの経理担当者の方は少なくないのではないでしょうか。そこで社会福祉法人会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、社会福祉法人の決算書の全体像を、拠点やサービス区分との関係も交えつつお伝えします。
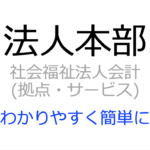
「法人本部って拠点区分・サービス区分のどちらなの?」そんな疑問を感じられた経理担当者の方が少なくないのではないでしょうか。そこで社会福祉法人会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、法人本部は拠点・サービス区分のどちらかをお伝えします。
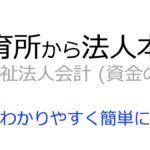
「保育所から一時的にお金を借りたのだけどどうしたらいい?」 そんな疑問をお持ちの社会福祉法人の経理担当者がいらっしゃるのではないでしょうか。「資金の貸借(組替使用)」というトピックですが、ルールがあります。そこで社会福祉法人の会計基準をわかりやすく簡単に解説する今回は、保育所から法人本部へ貸し付けたらどうなるかをお伝えします。
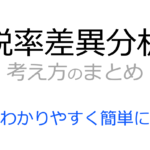
「税率差異分析の注記を作る方法を解説した良い記事ないかなぁ」 税効果会計の注記の中でも、トップレベルに難易度の高いのが、税率差異の分析の注記でしょう。でも、考え方を1つずつ紐解いていくと難しくはありません。そこで今回は、税率差異分析のの考え方を図解や数値例を使いながら、主なトピック別にわかりやすく簡単に解説します。

「フラット連結で連結財務諸表はどうやってるくるんだろう?」 連結担当を任されたけど、孫会社がいるグループだと簿記の教科書そのままとはいかず、悩ましいですよね。フラット連結がガッツリ解説されている本もあまり見かけません。そこで今回は、フラット連結のパターンの連結財務諸表の作り方をわかりやすく簡単に図解で解説します。
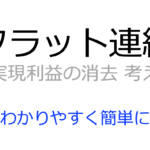
「フラット連結で連結財務諸表はどうやって作るのだろう?」 連結担当を任されたけど、孫会社がいるグループだと簿記の教科書そのままとはいかず、悩ましいですよね。フラット連結がガッツリ解説されている本もあまり見かけません。そこで今回は、フラット連結のパターンの連結財務諸表の作り方のうち「未実現利益の消去」をわかりやすく簡単に図解で解説します。
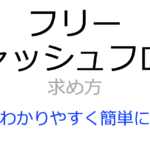
「フリーキャッシュフロー(FCF)ってどうやって計算するの?」 意味をつかめたら、次は計算方法が気になりますよね。そんなときは、「要するに何をしたい?」を押さえると、覚えなくても計算方法がわかるようになってきます。そこで今回は、フリーキャッシュフローの求め方を簡単数値例でわかりやすく解説します。
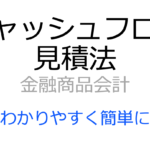
キャッシュフロー見積法は、貸倒引当金を計算する方法の1つですが、キャッシュフローの見積りが必要な上に、割引計算も出てきて難しい印象が強いのではないでしょうか。でも、考え方がわかれば、あまり難しくはありません。そこで今回は、キャッシュフロー見積法の考え方を、当初の利率を使う理由も含めて、わかりやすく簡単に解説します。
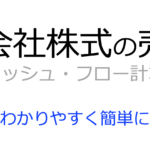
「子会社株式を売却したときに、キャッシュ・フロー計算書でどう表現するんだったかな?」子会社株式の取得よりもレアな売却で、うっかりキャッシュ・フロー計算書でどう書くかわすれちゃうことがありますよね。でも、考え方はシンプルで、「いくら増えた?」を考えるのがのポイントです。そこで今回は、子会社株式の売却のキャッシュ・フロー計算書の作り方をわかりやすく簡単に解説します。
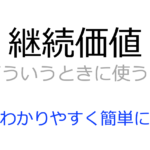
「継続価値ってどういうときに使うのだろう?」ぱっと見、どういうことを意味しているのかわかりにくいですよね。そんなときは「事業計画の有無」で考えるとイメージしやすいです。そこで今回は、継続価値はどういうときに使うのかを、注意点も合わせてわかりやすく簡単に解説します。

「リストリクテッド・ストックを子会社の役員に付与した場合の会計処理はどうするのかな?」いま注目の特定譲渡制限付株式について、仕訳を真正面から...
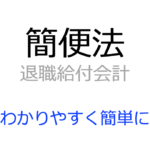
退職給付の計算は難しいイメージの強いトピックですが、要件を満たすとシンプルな計算をする簡便法の適用が認められています。そこで今回は、退職給付の簡便法の計算方法や期末自己都合要支給額とは何かをわかりやすく簡単に解説します。
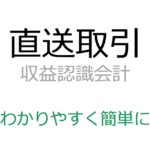
「直送取引って収益認識会計ではどう考えるのかな?」ものが仕入先から販売先へ直接移動するので、売上計上の時期や本人代理人取引の判定と仕訳など、検討ポイントがたくさんあります。そこで今回は、直送取引の収益認識と本人代理人判定をわかりやすく簡単に解説します。
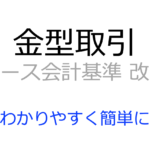
「金型を借りたらリースってどう考えたらいいんだろう?」新しいリース会計基準は抽象的な表現が少なくないので、イメージを掴むのが少し難しく感じますよね。そんなときは要件当てはめ例を見るのがコツです。そこで今回は、金型取引を改正リース会計基準の要件にあてはめるとどうなるのかを、取引図を交えながらわかりやすく簡単に解説します。
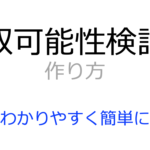
期末決算で税効果会計の担当を任されると、繰延税金資産の回収可能性検討表を作ります。そこで、具体的に何をどうするのかのイメージを掴むために、回収可能性検討表をわかりやすく簡単に解説した記事を紹介します。
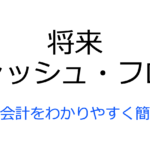
「減損処理しなきゃいけないかなぁ?」しばらく業績が良くないと、減損処理が必要か気になりますよね。これを減損損失の認識の判定といいますが、そこで「将来キャッシュ・フロー」という重要な用語が出てきます。そこで今回は、減損会計で使う将来キャッシュ・フローはどのように計算するかわかりやすく簡単に解説します。
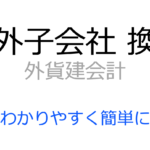
「海外に子会社がある場合の換算はどうするのだろう?」期末・期中平均などいろんな為替レートがあるので、在外子会社を連結決算へ取り込むときに少し悩みますよね。そんなときは、簡単な計算例を見るとイメージしやすくなります。そこで今回は、在外子会社の換算をどうするのかを、簡単な計算例を使いながら、わかりやすく簡単に解説します。
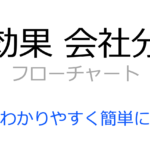
「会社分類の判定はどうする?」 税効果会計の担当を任されたらまず気になるのは、やはり会社分類の判定ですよね。会計ルールを見ると、難しい文章がいろいろ目にとまります。そんなときは、全体像を押さえてから会計ルールを読むと、理解が進みます。そこで今回は、税効果会計の会社分類判定のフローチャートをわかりやすく簡単に解説します。
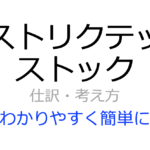
「リストリクテッド・ストックの仕訳はどうする?」特定譲渡制限付株式は会計処理を真正面から定めたルールがないものの、会計士協会から研究報告「インセンティブ報酬の会計処理に関する研究報告」が公表されています。そこで今回は、研究報告をベースにリストリクテッドストックの仕訳の考え方を図解でわかりやすく簡単に解説します。
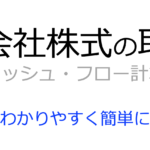
「子会社株式を取得したときに、キャッシュ・フロー計算書でどう表現するんだったかな?」たまに発生する子会社株式の取得で、うっかりキャッシュ・フロー計算書でどう書くかわすれちゃうことがありますよね。でも、考え方はシンプルで、「いくら減った?」を考えるのがのポイントです。そこで今回は、子会社株式の取得のキャッシュ・フロー計算書の作り方をわかりやすく簡単に解説します。
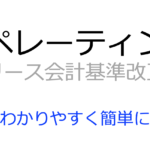
「オペレーティング・リースを資産計上するらしいけど、会計基準改正でどう考えるのかなぁ」 資産計上するという結論をたくさん目にしますが、具体的...
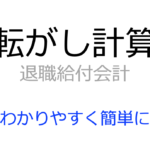
「退職給付の転がし計算ってどんな感じだったかな?」たしかに、よく耳に用語なのに、計算例をあまり見かけませんよね。実務指針にも載っていないので、どうやって計算するか知りたいところです。そこで今回は、簡単な数値例を使いつつ、退職給付の転がし計算をどうするのか、わかりやすく解説します。
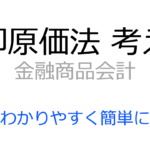
「償却原価法の考え方を知りたい!」「なぜ償却原価法の会計処理をするの?」なんとなく仕訳をしているかもしれない償却原価法ですが、気になる方は知識の振り返りにぜひ読んでみて下さい。今回のブログ記事では、簡単数値例を付けながら、償却原価法の理由と考え方をわかりやすく解説します。
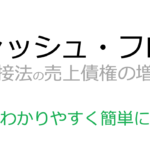
キャッシュ・フロー計算書の間接法は、何をしているのかイメージするのに時間がかかった経験はありませんか。そんな時は、簡単な数値例で仕組みを考えると見えてきますよ。今回は、間接法のキャッシュ・フロー計算書の売上債権の増減額をわかりやすく簡単に解説します。
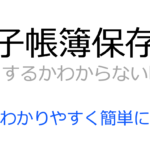
「電子帳簿保存法が何だかややこしそうでよくわからない!」いろんなところで耳にする「電子帳簿保存法」ですが、難しく聞こえる用語なので具体的に何をしたらいいのか、しなければいけないのか悩ましく感じている方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、どうすればいいかわからないときに読むブログ記事を書きました。
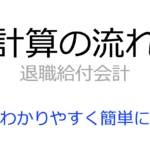
「退職給付会計が何をしてるか知りたい!」「退職給付の計算の流れはどうなってる?」経理部に配属されて数年経つと退職給付会計を任されることもあり、「難しい」と悩まれている方は少なくないのではないでしょうか。ポイントは「要するに何をしているのかを知ること」です。そこで今回は、退職給付の計算の流れを数値例とともに図解でわかりやすく簡単に解説します。
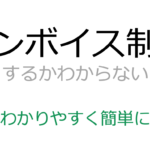
「インボイス制度がよくわからない!」 23年10月1日から始まるインボイス制度は、数ある税金でも難しいイメージの強い消費税の新しいルールなので、悩ましく感じている方は多いのではないでしょうか。そこで今回は、どうすればいいかわからないときに読むブログ記事を書きました。
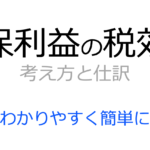
「子会社の留保利益の税効果の意味を知りたい!」難しい会計ルールの代表格である税効果会計の中でも、「留保利益の税効果」はひときわ難解なイメージの強いトピックです。とはいえ、「会計と法人税の一時的な差」という一時差異のポイントを押さえれば難しくありません。そこで今回は、子会社の留保利益の税効果の考え方と仕訳をわかりやすく簡単に解説します。
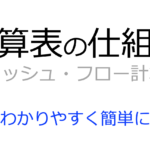
「キャッシュフロー精算表が書けるようになりたい!」決算の終盤に作るキャッシュ・フロー計算書の担当を任されたら精算表を作りますが、作り方のイメージが掴みにくいですよね。とはいえ、仕組みが分かれば書き方をマスターするのは難しくありません。そこで今回は、キャッシュフロー精算表の仕組みや書き方をわかりやすく解説し、やり方をつかんで頂きます。
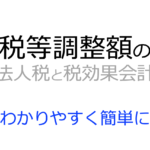
「法人税等調整額は、別表でどのように書けばいい?」税効果会計のルールが理解できたら、次は法人税の別表の書き方が気になりますよね。難しいイメージがありますが、そもそも論を押さえると、別表の書き方は簡単です。そこで今回は、数値例を使いながら法人税等調整額の別表(4、5-1)の書き方をわかりやすく簡単に解説します。
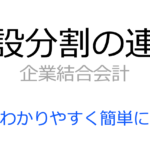
新設分割をする場合に連結決算ではどのように仕訳するのでしょうか?ポイントは、個別財務諸表のときと同じく「投資(=支配)が継続しているか?」で、それを連結グループの視点から見ます。そこで今回は、新設分割の連結財務諸表での仕訳を図解でわかりやすく簡単に解説します。
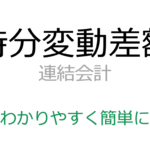
「持分変動差額の仕訳は何をしているのか知っておきたい!」 連結決算の仕事を任されて持分変動差額の会計処理が必要になったら、自信を持って仕訳をしたいですよね。理解するポイントは2つあります(みなし売却の意味・わかりやすい図解)。そこで今回は、連結や持分法の会計処理で出てくる持分変動差額を、図解でわかりやすく簡単に解説します。
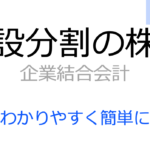
分割型の新設分割の会計ルールでは、株主の会計処理がたくさん定められています。そこで今回のブログ記事では、図解を使いながら、分割型の新設分割の株主の会計処理【個別財務諸表編】のポイントをわかりやすく簡単に解説します。なお、解説をシンプルにするために、「対価は株式のみ」を前提とします。
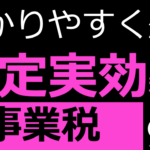
法定実効税率の計算式で「1+事業税率」が出てきますが、なぜ1+事業税率で合計税率を割る必要があるのか悩んでしまいますよね。答えは「損金になるから」ですが、スッキリ理解するにはポイントが2つあります。そこで今回は、法定実効税率の計算式で、1+事業税率で割る理由をかわかりやすく簡単に解説します。
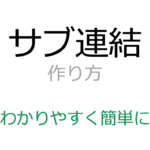
「サブ連結で連結財務諸表を作りたい」 連結担当を任されたけど、孫会社がいるグループだと、簿記の教科書そのままとはいかず、悩ましいですよね。そこで今回は、サブ連結のパターンの連結財務諸表の作り方をわかりやすく簡単に図解で解説します。
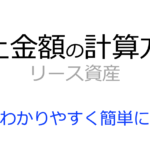
「リース資産の金額はいくらにしたらいい?「計算方法はどうする?」ファイナンス・リース取引の判定が理解できたら、次は仕訳の金額が気になりますよね。そこで今回は、「リース資産の計上金額」に注目して、計算方法はどうするかわかりやすく簡単に解説します。
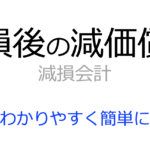
「減損損失を計上したら、その後の減価償却計算はどうなる?」「耐用年数は短縮するの?」減損処理は頻繁に行うものではないので、減損処理をした後どうするのかうっかりしちゃうことがありますよね。そこで今回は、減損後の減価償却や耐用年数の短縮はどうするのかを、取得価額(取得原価)の取扱いとともに、わかりやすく簡単に解説します。
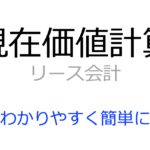
「リース料総額の割引現在価値計算ってどうするの?」確かにぱっと見は難しそうですが、考え方とか計算方法がわかれば、シンプルですよ。そこで、リース会計を図解でわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、リースの現在価値基準の計算方法を、割引率の考え方とともにお伝えします。
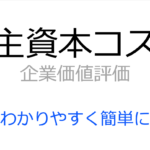
「株主資本コストはなぜ難しい数学の計算式なの?」「出し方や意味を簡単に知りたい!」数学が得意な人じゃない限りは、株主資本コストの計算式はCAPMという理論を使うのですが、計算式を見ると構えちゃいますよね。そこで今回は、株主資本コストの出し方や意味を具体例とともにわかりやすく解説します。
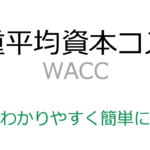
「加重平均資本コスト(WACC)」は企業価値評価でよく出てくる用語ですが、考え方や求め方を聞かれると曖昧な部分があったりしますよね。そこで企業価値評価をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、加重平均資本コストの考え方や求め方を、使う理由や役割も交えながら解説します。
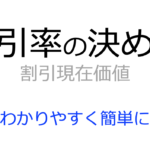
「割引率はどのように決めるの?」 割引率の考え方がわかったら、次はどうやって決めるか気になりますよね。でも、割引率の考え方をベースに考えると、そんなに難しくはありません。ポイントは「リスクに見合った見返りを要求する」です。そこで今回は、割引率の決め方を図解でわかりやすく簡単に解説します。
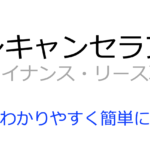
ファイナンス・リースは、固定資産を持っているのと同じような会計処理をしますが、判定は2種類の要件があります。2つ目の要件はノンキャンセラブルで、こちらもいくつかのトピックがあります。そこでリース会計基準をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、ファイナンス・リースの判定のノンキャンセラブルを解説します。
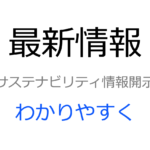
23年3月期の有報から始まる「サステナビリティ情報開示」の情報はいろんなところでみかけますが、最新情報をまるっと知るにはこちらの記事をご覧ください。当ブログでは、サステナ情報開示の最新情報をはじめ、開示事例も紹介します。
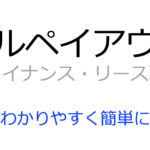
ファイナンス・リースは、固定資産を持っているのと同じような会計処理をしますが、判定は2種類の要件があります。そのうちの1つがフルペイアウトなので、リース会計基準をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、ファイナンス・リースの判定のフルペイアウトを解説します。
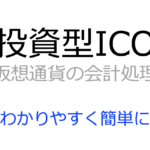
「ICOの会計処理はどうするのかな?」仮想通貨の取引の会計処理のルールが整備され、ICOにもフォーカスが当たりました。では、具体的にどんな会計処理が求めらるのでしょうか。今回は、投資型ICOの会計処理の入門知識を、わかりやすく簡単に図解で解説します。
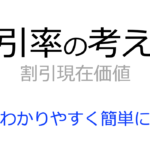
「割引率」の考え方がわかると、割引現在価値の計算の仕組みがかなりクリアに見えてきます。そこで今回は、割引率の考え方を、初心者の方にもわかるような図解でわかりやすく簡単に解説します。
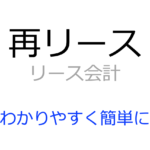
リース取引の中には、リース契約期間が終わった後も(割安なリース料で)リース資産を使えることがあり、再リースと呼ばれています。この場合に、リース料やリース期間を使って、ファイナンス・リースの判定をどうするのでしょうか?今回は、リース会計での再リースの仕訳や意味(=考え方)をわかりやすく簡単に解説します。
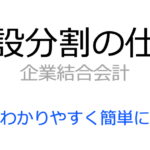
「新設分割の仕訳ってこれで合っているかなぁ」大半の会社では新設分割を頻繁にすることはないので、新設分割の仕訳を任されると不安ですよね。でも、図解でひも解くと、意外にシンプルです。企業結合会計を図解でわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、新設分割の会計処理の個別財務諸表編を紹介します。
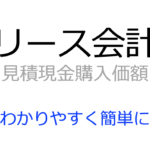
リース会計の判定手続をするときに見積現金購入価額が出てきますが、意味や計算方法はご存知でしょうか?「なんとなくわかるんだけど」という方がいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、リース会計の見積現金購入価額をわかりやすく簡単に解説します。
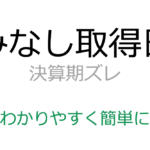
新しく買収した子会社の決算期が親会社と違うことはよくあります。そんな時に出てくるトピックが「みなし取得日」ですが、具体的にいつなのか、そして損益計算書はどの期間を取り込むのか判断に迷うことがありますよね。そこで今回は、決算期ズレ子会社を決算へ取り込む時のみなし取得日との関係を、損益計算書の取り込みとともにわかりやすく簡単に解説します。
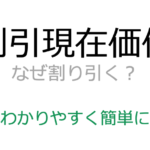
「割引現在価値の計算って何となくわかるんだけど、なぜ割り引くのかスッキリしないなぁ」テキストで「今のお金と将来のお金は価値が違う」と説明されていますが、「なるほど!」とまでは思わないですよね。そこで今回は、なぜ割引計算するかを図解でわかりやすく簡単に解説します。
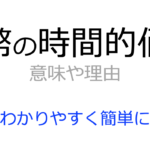
「貨幣の時間的価値」は最近の会計ルールでたくさん目にすることがあると思います。でもどういう意味かを聞かれるとはっきり答えるのは簡単ではないですよね。そこで当ブログでは、貨幣の時間的価値とは何かを、意味・理由、そして割引率とともにわかりやすく簡単に解説します。
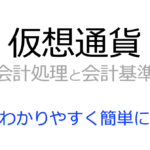
「うちの会社が仮想通貨を購入したんだけど、会計処理の仕方どうするの?」仮想通貨は法律の名前も難しくて、どこを調べたらいいか迷いますよね。でも、仮想通貨の会計処理はある程度整備されているので、当ブログで会計基準の最新動向と合わせて、サクッとポイント解説しちゃいます。
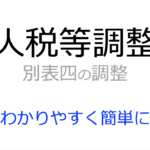
「法人税等調整額って別表四で調整しなきゃいけないの?」「書き方が気になる」こんな悩みをお持ちの方向けのブログ記事です。法人税では税効果会計は使わないので、別表四の調整が必要になります。利益が増減しているからです。そこで今回は、法人税等調整額の別表四での書き方を解説します。
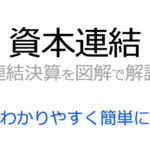
「投資と資本の相殺消去(資本連結)の仕訳をスッキリ理解したい」確かに、個別決算の簿記の知識をベースに考えると、なぜ相殺消去するのかの答えがわからないですよね。理解のポイントは、①超簡単な数値例を使う②図解でイメージの2つです。連結決算をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、投資と資本の相殺消去の仕訳を紹介します。
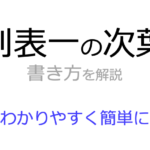
「別表一の次葉の書き方のイメージをつかみたい!」別表一は税額を計算する申告書ですが、次葉はそのサポートの役割を果たします。そこで今回は、別表一の次葉の書き方を、申告書の数値例をまじえつつ、わかりやすく簡単に解説します。
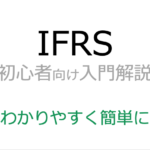
「IFRSの論点を初心者向けにわかりやすく解説してほしい!」 日本の会計ルールはIFRSの影響を大きく受けているので、IFRSの論点をしっておきたいですよね。でも、原文は英語ですしとっつきにくいのではないでしょうか。そこで今回は、IFRSの論点を初心者向けに、図解でわかりやすく簡単に入門解説します。
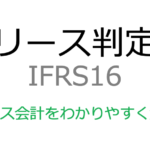
「リース会計基準が改正されるので、IFRS16号でのリース取引の判定の仕方を知っておきたい」そんな方向けのブログ記事です。そこで今回は基礎編として、IFRS16のリースの判定をわかりやすく簡単に図解で解説します。
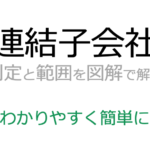
「ルールが複雑なので、連結の子会社の範囲と判定の仕方を教えてしてほしい」たしかに色々細かいルールがあって、理解しにくいですよね。ポイントは支配しているか否かなので、支配の視点でルールを眺めると見えてきます。そこで今回は、連結の子会社の範囲と判定を図解でわかりやすく簡単に解説します。
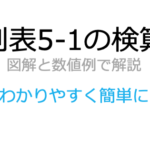
「別表5-1を作ったので正しいか検算して確かめたい」たしかに別表5-1はいろんな数字が集まってくるので、しっかり正しく作れたのか不安に感じますよね。検算のポイントは別表5-1のしくみをしることですが、難しいイメージもあります。そこで今回は、別表5-1の検算の方法を簡単な数値例と図解でわかりやすく解説します。なお、当ブログ記事では、利益積立金額部分のみを対象とします。
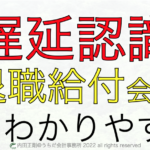
「遅延認識や即時認識って何?」「何がどう違うのか知りたい!」たしかに難しい用語なので、そもそも何をしているのか気になりますよね。簡単にいうと、「数理計算上の差異」の処理のことですが、仕組みを知りたいところです。そこで、退職給付会計をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、遅延認識と即時認識にフォーカスします。
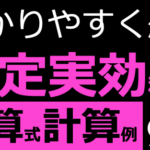
「法定実効税率の計算式が難しい」はじめて計算式を見たときは、何をしているか分からず困っちゃいましたよね。うちだも、計算式をはじめて見たときは、頭の中に「?」がたくさん出てきたことを覚えています。そこで税効果会計をわかりやすく解説するシリーズの今回は、法定実効税率とは何なのかを、計算式と具体例とともに解説します。
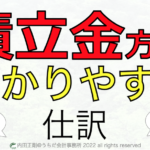
「圧縮記帳の積立金方式の仕訳が難しい」「積立金方式の税効果会計の仕訳を考えたら混乱しちゃう」たしかに難しいイメージが強いですよね。でも、理解のポイントは「法人税の儲けの計算の仕方を知る」だけで、至ってシンプルです。そこで、今回は「圧縮記帳の積立金方式の仕訳」を、税効果会計の解説と合わせて、図解を使いながらわかりやすく簡単に解説します。
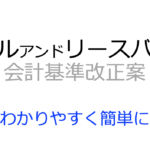
「セールアンドリースバック取引の会計処理が気になる」 リース会計基準の改正案が公表され、セールアンドリースバック取引も考え方が整理されました。そこで今回は、セールアンドリースバックの会計基準改正案をわかりやすく簡単に解説します。
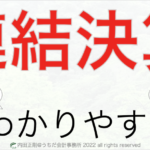
「連結決算の全体像を知りたい!」連結決算では連結仕訳や連結子会社の範囲をはじめいろんなトピックが出てくるので難しいですよね。でも、「何をしているか?」がわかれば、スムーズに理解が進みます。今回の連結決算をわかりやすく解説するシリーズの今回は、連結決算とは何かを図解でわかりやすく簡単に解説します。
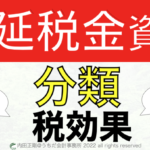
「繰延税金資産の分類を判定したら限度額はいくらなの?」回収可能性の会社分類を判定したら気になりますよね。限度額は5つの分類ごとにはっきり決まっているので、数値例を使ってまとめて覚えるのがベストです。そこで、税効果会計をわかりやすく解説するブログシリーズの今回は、繰延税金資産の分類と限度額の関係と変更の影響を解説します。
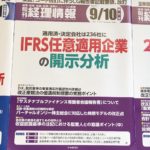
「収益認識の期末の注記を監査法人と協議しなきゃいけない!」「収益認識会計基準では有価証券報告書で何を注記するの?」悩ましいトピックが多いですよね。そこで今回は、「収益認識の注記の監査法人との協議ポイント」をわかりやすく簡単に解説した雑誌を紹介します。
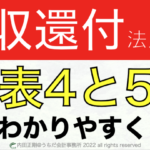
「未収還付法人税等ってどんな仕訳をするの?」「別表4や別表5-1ではどんな調整をするか知りたい」法人税では、納税充当金のように会計と違った考え方で調整することがあるので、確かに知りたいですよね。そこで法人税の申告書をわかりやすく解説するシリーズの今回は、未収還付法人税等の仕訳や別表4, 別表5-1の書き方を解説します。
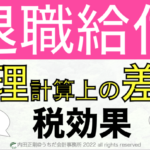
「数理計算上の差異の税効果が難しくてわからない」確かに数理計算上の差異は、遅延認識とか即時認識とか難しい用語がたくさん出てきますよね。混乱しちゃった時は「会計と法人税の一時的な差」という視点で見ると、サクッと理解できちゃいますよ。そこで今回の退職給付のブログ記事は、「数理計算上の差異の税効果はなぜ発生するのか?」や、繰延税金資産の回収可能性・組替調整の税効果などのトピックをわかりやすく解説します。
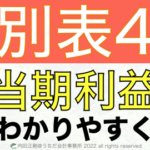
「別表4の一番上に書いてる当期利益って税引き前or後のどっち?」「別表4は税金を計算するための資料なのに税引き後ってどういう意味?」なんだか混乱しちゃいますよね。答えは「目的によって違う利益を使う」です。そこで今回は、法人税別表4の当期利益が、税引前or税引き後のどちらかを理由とともにわかりやすく簡単に解説します。
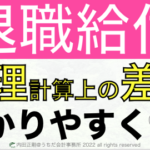
数理計算上の差異は難しいので、どんな仕訳をするかわかりにくいですよね。でも、発生原因が理解できれば数理計算上の差異はサクッとわかります。そこで今回のブログでは、数理計算上の差異がなぜ発生するのか(=原因)や、プラス・マイナス(=借方・貸方)の時にどんな仕訳をするのか、そして未認識数理計算上の差異について、わかりやすく簡単に解説します。
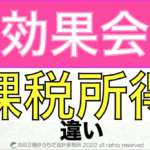
税効果会計で「課税所得の見積り」とか「一時差異等加減算前課税所得」が出てきますが、法人税の課税所得とどんな違いがあるのか悩みますよね。ズバリ結論は一時差異が解消する前の課税所得で、「解消前の」という部分に法人税とは違いがあります。

「監査対応が難しいからコツを教えてほしい」ますます厳しくなる監査対応で、頭を悩ませる場面が多いのではないでしょうか?解決のコツは「先回り」ですが、どんな準備をしたらいいか知っておきたいですよね。そこで、このページでは、内田正剛が図解を使って監査対応のコツをわかりやすく簡単に解説するセミナーの概要をお伝えします。

「収益認識会計基準をわかりやすく解説してほしい!」難しい用語がたくさん並んでいる収益認識会計基準ですが、売上の会計ルールなので是非とも知っておきたいですよね。そこで、このページでは、内田正剛が図解を使って収益認識会計基準をわかりやすく簡単に解説するセミナーの概要をお伝えします。
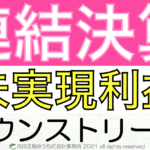
「連結決算の未実現利益消去で、ダウンストリームってどんな仕訳をするの?」つい うっかりしちゃいますよね。そこで連結決算の未実現利益消去をわかりやすく簡単に 解説するシリーズの今回は、ダウンストリームをお伝えします。

「収益認識会計基準のおすすめの本やnoteを知りたい!」そんな方にお伝えするブログ記事です。収益認識会計基準をわかりやすく簡単に解決するシリーズの今回は、わかりやすい書籍やnoteを紹介します。
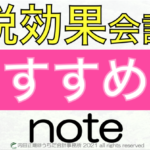
「税効果会計のおすすめの本やnoteを知りたい!」そんな方向けのブログ記事です。税効果会計をわかりやすく簡単に解決するシリーズの今回は、わかりやすい書籍やnoteを紹介します。
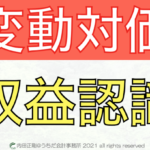
「変動対価の仕訳の仕組みが知りたい!」「変動対価って何?定義は?」そんな方向けのブログ記事です。収益認識会計基準をわかりやすく簡単に解決するシリーズの今回は、変動対価の仕訳と定義をお伝えします。

「出荷基準の要件は何?」「出荷基準はなぜ認められる?」そんな方向けのブログ記事です。収益認識会計基準をわかりやすく簡単に解決するシリーズの今回は、出荷基準の通常の期間と要件をお伝えします。
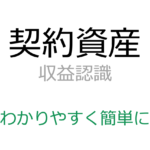
「契約資産と債権って何が違う?」「契約資産の意味を知りたい!」そんな方向けのブログ記事です。収益認識会計基準をわかりやすく簡単に解決するシリーズの今回は、契約資産と債権(売掛金)の違いを、仕訳や表示とともに解説します。
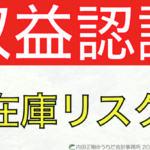
「在庫リスクって何?」「どんなリスク?」「なぜ収益認識で出てくるの?」収益認識の検討をしていたら時々出てくる在庫リスクですが、気になっちゃいますよね。そこで収益認識会計基準をわかりやすく簡単に解説するシリーズの今回は、在庫リスクを解説します。

「法人税の申告期限と納付期限の延長のしくみを知りたい」難しい条文を読むと、時々混乱しちゃいますよね。そこで、法人税をわかりやすく解説するシリーズの今回は、「法人税の申告期限と納付期限の延長」をわかりやすく簡単に解説します。
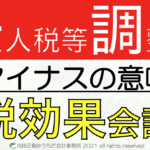
「法人税等調整額がマイナスってどういう意味?」法人税は費用なので、損益計算書で法人税等調整額がマイナスになってたら意味を知りたくなりますよね。そこで税効果会計をわかりやすく簡単に解説するブログの今回は、法人税等調整額がマイナスの意味を解説します。